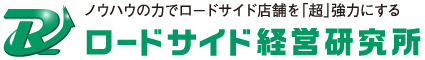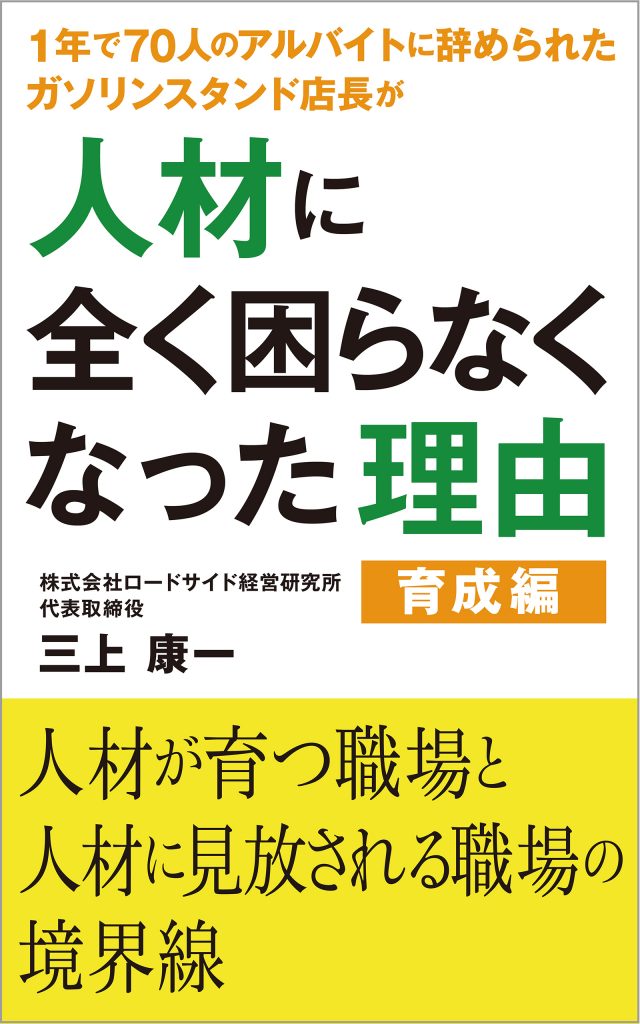1.部下の独立により裏切られないために
(1)裏切られたと「感じた」経営者
ある美容院経営者が発した以下のご相談に触れる機会がありました。
「これまで様々なスタイリストを育ててきましたが、一人前になるまで技術などを教えても、数年で独立のために退職されたり、中には顧客情報を盗んで私の店の近くに独立するなど、恩を仇で返されたりして、人材育成に意味があるのか?と思います。他の経営者の方々は、どのような気持ちで人を育てているのでしょう?」
この経営者が考えるべきことは、人材育成の目的です。これが明確かつ正しいものになっていないと部下の独立により、自分が被害者になってしまう可能性が高まるでしょう。では、以下で人材育成の目的を見ていきます。
(2)公的な目的を持つ
極端な例を挙げますが、美容室経営者が持つ人材育成の目的が「部下に仕事を任せて遊びに行きたい」という私的なものだと、部下に独立されると困ります。経営者は遊びに行けなくなるからです。これに対して、その目的が「この街に美しい人を増やす」という公的なものだと、部下に独立されても経営者は被害者になり得ません。
特定の商業集積地へ消費者が行く確率を示したハフ・モデルによると、地域の集客力は店舗数にも影響を受けますので、街にもう1軒美容室が増えることは、他の街からこの街の美容室を利用しに来る方が増加することを意味しています。
さらに、独立されるということは、地域の競争業者が増えることから、新規顧客の集客策やその固定化といったマーケティングの施策が切磋琢磨されることも考えられますし、同じ経営者として、悩みを共有したり情報交換をしたりすることも可能となります。
人材育成の目的が「この街に美しい人を増やす」だとしたら、上記を通じてその目的が実現されやすくなります。つまり、私的な目的で人材育成をすると、独立した部下が加害者となり、独立された経営者が被害者となりやすいのですが、公的な目的で人材育成をすると、経営者も部下も、そして顧客も世間も、よりハッピーになることが期待できます。
ただし、まっとうな手段で独立していただく必要があります。前述の経営者の悩みにあった「顧客情報を盗んで」という点を考えてみたいと思います。
(3)部下を成功者にするための指導をする
顧客情報を盗んで商売をすることは「邪道」です。そもそもの考え方が邪道ですから、その商売は繁栄するべくもありません。顧客情報を盗んで独立しようとする者を責めることよりも、結果としてそのようなお膳立てをする形になったこの経営者は、ご自身の育て方に根本的な間違いがなかったか、振り返ってみる必要があるでしょう。
正々堂々と商売できない人材が、自分の元から独立したことで、経営者が清々しているならまだしも、この経営者はそれを悔しがっているわけです。これは、自店のことや短期的なことのみに目が奪われており、公的かつ中長期的な視点が欠けていると言えるでしょう。
リクルート出身でJリーグのトップを務めていた村井満氏は、リクルートに在籍していた頃、人材育成に注力し、社外から引き抜きに遭うような人材を会社として支援するべく、そのような人材が退職する際に1,000万円を付与する制度を設けました。
社外に羽ばたく人材を多数輩出する組織には、人材育成の風土が醸成されますので、成長したい人材が集まるでしょうから、独立のために退職されても、その事業者は人材不足に陥る可能性は低くなります。
独立で部下に裏切られたと感じる経営者は、人材育成の目的が明確になっているか、まっとうな商売のできる人材を育てようとしているか、検討する必要があると思いますが、いかがでしょうか。
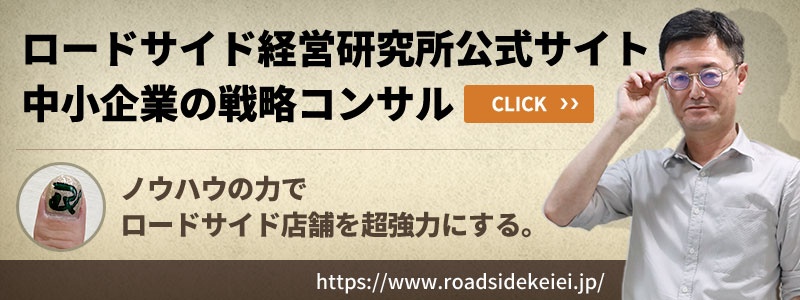
2.メルマガ会員様募集中
メルマガ会員様には、リアル店舗の現場経験20年以上、コンサルティング歴10年以上【通算30年以上のノウハウ】を凝縮した【未公開のコラム】を優先的に配信しています。
メルマガ登録はこちらから↓↓↓
https://ssl.form-mailer.jp/fms/33bd5af2611330
3.電子書籍のご案内
1年で70人のアルバイトに辞められたガソリンスタンド店長が人材に全く困らなくなった理由:育成編