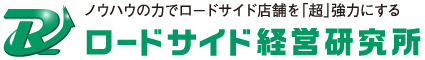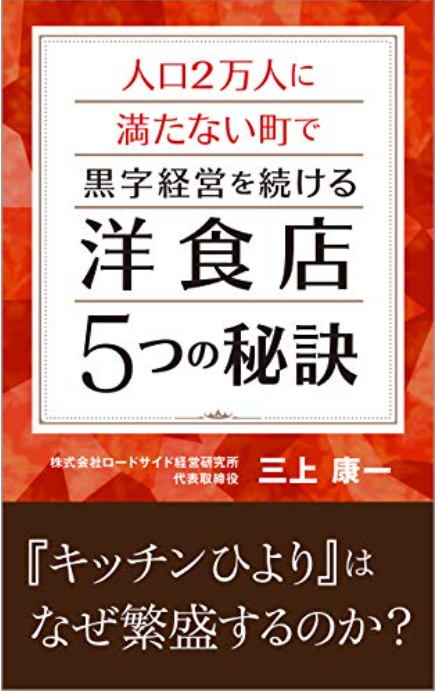その自動車整備工場は、観光地に近い場所に立地しており、出先で事故や車両トラブルに見舞われたドライバーからの連絡を受け、レッカー移動や修理などを実施するロードサービスを大きな収益源としていました。
ところが、新型コロナウイルスの影響により、外出する方が減少してしまった結果、ロードサービスの依頼も激減し、売上が大きく低下してしまいました。そこで、小規模事業者持続化補助金を活用し、インターネットで自社の訴求力を高めようと考え、結果として当該補助金に採択されました。
当コラムでは、同社の事例を参考に小規模事業者持続化補助金の採択可能性を高める計画書の書き方を見ていきますが、事業者が単独で当補助金に応募する際は、原則として以下の書類を作成し、締め切り日までに送付する必要があります。
様式1-1 小規模事業者持続化補助金事業<一般型>に係る申請書
様式2-1 経営計画書兼補助事業計画書①
様式3-1 補助事業計画書②
様式4 事業支援計画書
様式5 補助金交付申請書
今回は、様式2-1経営計画書兼補助事業計画書①を見て行きますが、その構成は以下となっています。
<応募者の概要>
<経営計画>
<補助事業計画>Ⅰ.補助事業の内容
今回は、様式2-1経営計画書兼補助事業計画書①の<経営計画>を見て行きますが、その構成は以下となっています。
1.企業概要
2.顧客ニーズと市場の動向
3.自社や自社の提供する商品・サービスの強み
4.経営方針・目標と今後のプラン
今回は、3.自社や自社の提供する商品・サービスの強みを見ていきます。なお、当コラムの内容は2020年9月8日時点の情報に基づくものとなっています。
1.持続化補助金でコロナに立ち向かう自動車整備工場の事例「自社や自社の提供する商品・サービスの強み」の書き方
持続化補助金でコロナに立ち向かう自動車整備工場の事例「自社や自社の提供する商品・サービスの強み」の書き方(1)内容を切り分ける
当欄のタイトルは「自社や自社の提供する商品・サービスの強み」であり、2つのテーマが盛り込まれています。これを1つの文章でまとめようとすると、冗長性が高まり、読み手に伝わりにくくなるリスクが高まります。
そこで弊社では「自社の強み」、「自社が提供する商品・サービスの強み」と見出しを設け、切り分けて記載することをお勧めしています。さらに「自社の強み」は、次に掲げる切り口を設けると強みを見出しやすくなるでしょう。
持続化補助金でコロナに立ち向かう自動車整備工場の事例「自社や自社の提供する商品・サービスの強み」の書き方(2)「自社の強み」は経営資源の切り口を使う
弊社では、「強み」を「顧客に対して価値を提供することができ、競合に対して優位性がある経営資源」と定義づけしています。そして、経営資源とは人・物・金・情報で構成されますので、当事例では以下の観点から「自社の強み」を洗い出しました。
【人的資源の強み】経営者の経歴、経営者やスタッフのスキル、キャラクターなど
【物的資源の強み】整備に関する設備、工場の立地など
【財務的資源の強み】借入状況や返済状況、金融機関との関係性など
【情報的資源の強み】受発信している情報、蓄積してきたノウハウなど
これらの切り口から検討した結果、同社の場合は以下の内容の強みを抽出することができました。
【人的資源の強み】
- 後継者が存在し、中長期的な視点から事業展開の検討が可能なこと
- 各種資格保有者が在籍し、専門性を活かすことが可能であること
【物的資源の強み】
- レッカー車など各種の特殊車両を保有し、多様なロードサービスに対応できること
- 事業展開に活用できる土地を保有していること
【情報的資源の強み】
- 創業○十年の歴史があり、地域での知名度・信頼性が高いこと
持続化補助金でコロナに立ち向かう自動車整備工場の事例「自社や自社の提供する商品・サービスの強み」の書き方(3)サービス業としての強みを検討する
次に「自社の提供する商品・サービスの強み」を検討します。同社が提供する商品、つまりモノは中古車や新車といった自動車ですが、これらは同業他社と比較しても明確な差別的優位性は見出せませんでした。反面、上記の「自社の強み」を活用した品質の高い自動車整備やロードサービスの提供は、差別的優位性が存在することから、提供するサービスの強みを列挙しました。
今回は、採択の可能性を高める「3.自社や自社の提供する商品・サービスの強み」として、(1)内容を切り分ける、(2)「自社の強み」は経営資源の切り口を使う、(3)サービス業としての強みを検討する、を述べました。
次回は「4.経営方針・目標と今後のプラン」を見て行きますが、これまで同社を事例として、当補助金計画書の記載方法を述べたコラムは以下となります。
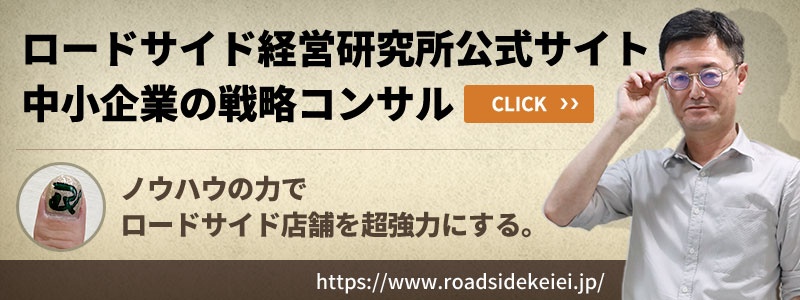
2.当コラムの解説動画
3.小規模事業者持続化補助金の申請書類作成をサポートします。
弊社の1,000件を超える支援実績を通じて蓄積してきたノウハウを活用して、採択の可能性を高める計画書作成のお手伝いをいたします。詳しくはこちらから↓↓↓
4.メルマガ会員様募集中
メルマガ会員様には、リアル店舗の現場経験20年以上、コンサルティング歴10年以上【通算30年以上のノウハウ】を凝縮した【未公開のコラム】を優先的に配信しています。
メルマガ登録はこちらから↓↓↓
https://ssl.form-mailer.jp/fms/33bd5af2611330
5.電子書籍のご案内(2020年7月8日発行 定価1,072円)
人口2万人に満たない街で黒字経営を続ける洋食店5つの秘訣