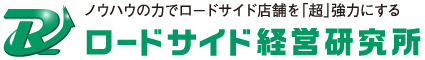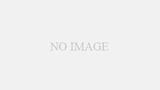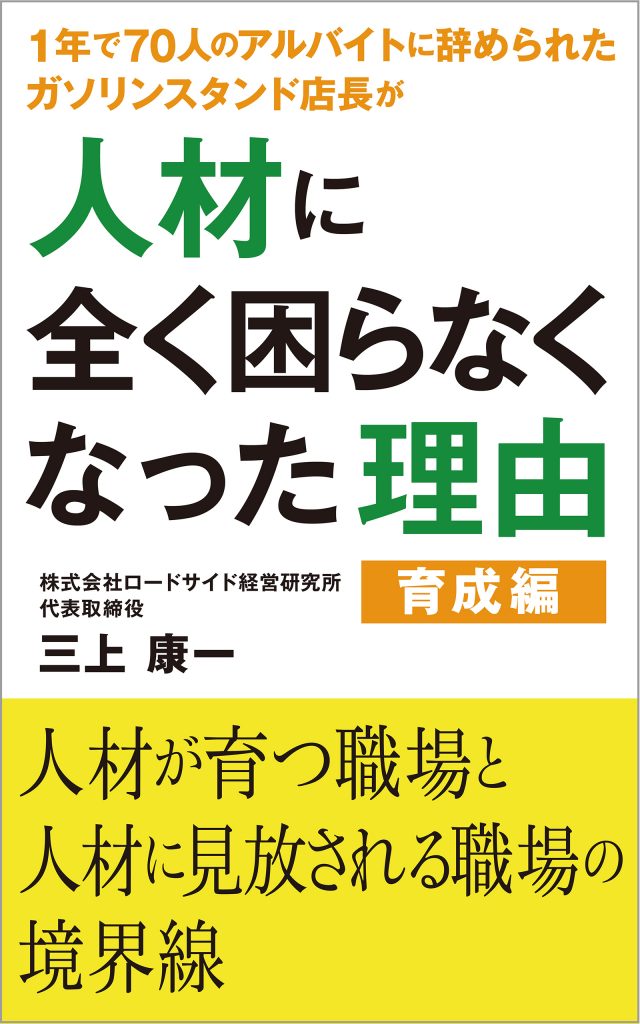1.ガソリンスタンドが人手不足を克服するために
私は、ガソリンスタンドの運営会社に21年間勤務し、ガソリンスタンドの現場に身を置いてきました。そのうちの13年間は店長を務めましたが、店長になって10年間ほどは、深刻な人手不足に深く深く悩まされました。
勤務シフトを作成する都度、アルバイトスタッフに「○日に人がいないので、なんとか少しの時間でも出社できないかな」とお願いをし、ようやくシフトが出来上がる有様でした。出社できるスタッフが全くおらず、朝から晩まで1人で1日15時間の勤務が当たり前の時期もありました。
しかし、今回のコラムでご紹介する内容を通じ、店長として最後の3年間ほどは、人手不足に苦しむことがなくなっただけでなく、私含め全スタッフが定時で退社し、年間休日も完全に消化できるようになり、店舗の業績も向上しました。また、大学生のアルバイトスタッフが就職先として当店を選んでくれるようにもなりました。
多くのガソリンスタンドが人手不足に苦しんでいます。人手不足なので、洗車やエンジンオイル、タイヤなどガソリン以外の商品(油外商品)が売れない、その結果儲からない、儲からないから募集広告の費用が捻出できない、これに耐え切れず既存スタッフが退職し、さらに人手不足が深刻になる、という負のスパイラルに陥ってしまいます。今回のコラムでは、上記の経験を踏まえ、このような負のスパイラルを断ち切るための情報を提供していきます。
(1)人手不足をこれ以上深刻にさせない
物騒な例ですが、大量出血で病院に担ぎ込まれた怪我人には輸血が必要です。よって、その治療は真っ先に輸血だけをするでしょうか。その前に止血をしないと、輸血した血液は単に患者の体を素通りし、洩れるだけになります。
人手不足に喘ぐ職場は、人材流出を止める前に新規採用に走りがちですが、まずは止血策を講じる必要があります。止血策とは従業員満足を上げ、定着率を向上させることです。この従業員満足の要素は、標準化・能力開発・モチベーションの3つとされています。
標準化には、業務マニュアルの整備、経営理念の策定が挙げられます。特に、接客の現場ではマニュアルに定められていない対応が求められる場合が多いわけですが、従業員の判断基準となる経営理念は定められているか、もし定められているとしたら、現場に浸透しているか、を検討します。以下のコラムを参考にしてください。
また、能力開発には、OJT、Off-JT、自己啓発がありますが、OJTを有効なものにしておく必要があります。以下のコラムを参考にしてください。
そして、モチベーションに関しては、ハーズバーグの動機付け=衛生理論に基づいた取組みが有効でしょう。以下のコラムを参考にしてください。
(2)募集広告と面接内容の充実化
従業員満足度を向上させながら、店頭や新聞折込、ネットなどの募集広告を活用しますが、応募者が多い募集広告は、以下の5W3Hが明確になっているものです。
- When(何時から何時まで働けるのか)
- Where(働く場所はどこか)
- Who(誰と働くのか)
- Why(なぜ募集しているのか→どんなビジョンを達成しようとして募集しているのか)
- What(何の仕事をするのか)
- How(どのように教育訓練がなされるのか)
- How many(どのくらいの期間働いて欲しいのか)
- How much(いくらの給与なのか)
誰と働くのかを告知するためには、働いているスタッフの写真や、働くスタッフの声を広告媒体に掲載します。
なぜ募集しているのか、を告知するためには、自社の経営理念、経営ビジョンを示します。このビジョンを経営理念に基づき達成するために、人材が必要であることを訴求します。実業家の松本晃氏がカルビー(株)の会長を務めていた頃に「生まれも育ちも異なる人と一緒に働くわけですから『当社はこんな理由で存在し、こんな夢を持っています。現在の人材だけでは達成できませんので、同じ志を持った方、是非いらして下さい』といった内容が必要」と述べています。
さらに、採用面接の際は、以下の5つの項目のどちらを重視するのか、それが自店と一致しているかを見極めます。
- 情を重視/理を重視
- 行動を重視/思考を重視
- 協調を重視/競争を重視
- 伝統を重視/革新を重視
- スピードを重視/緻密さを重視
人材に関しては以下のコラムも参考にしてください。
(3)アルバイトスタッフの正社員登用
学生さんがガソリンスタンドでアルバイトすることは、ガソリンスタンドでインターンシップ(職業体験)を行うことに繋がります。最初は、軽い気持ちでアルバイトしていた学生の従業員満足が高まり、職場に愛着を感じるようになると、そのスタンドが就職先の候補となります。
アルバイトスタッフの正社員化は、法定福利費の半額を会社が負担するので、アルバイト時代よりも人件費が高くなりますが、長期のインターンシップを経験した方が正社員になるわけですから、まっさらな新人を雇うより教育面などで低コストとなります。また、正社員という立場で責任を与えられ、即戦力として働いてくれるのですから、油外販売の貢献度が高くなる可能性もあります。
今回のコラムでは、人手不足を克服するために(1)人手不足をこれ以上深刻にさせない、(2)募集広告と面接内容の充実化、(3)アルバイトスタッフの正社員登用、を挙げました。これらを参考に人手不足対策を進めていきましょう。
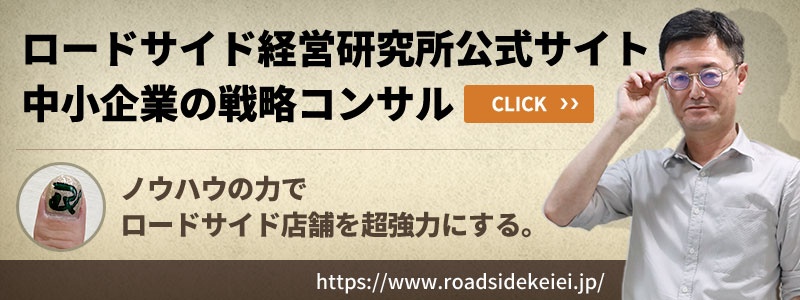
2.当コラムの解説動画
3.メルマガ会員様募集中
メルマガ会員様には、リアル店舗の現場経験20年以上、コンサルティング歴10年以上【通算30年以上のノウハウ】を凝縮した【未公開のコラム】を優先的に配信しています。
メルマガ登録はこちらから↓↓↓
https://ssl.form-mailer.jp/fms/33bd5af2611330
4.電子書籍のご案内
1年で70人のアルバイトに辞められたガソリンスタンド店長が人材に全く困らなくなった理由:育成編